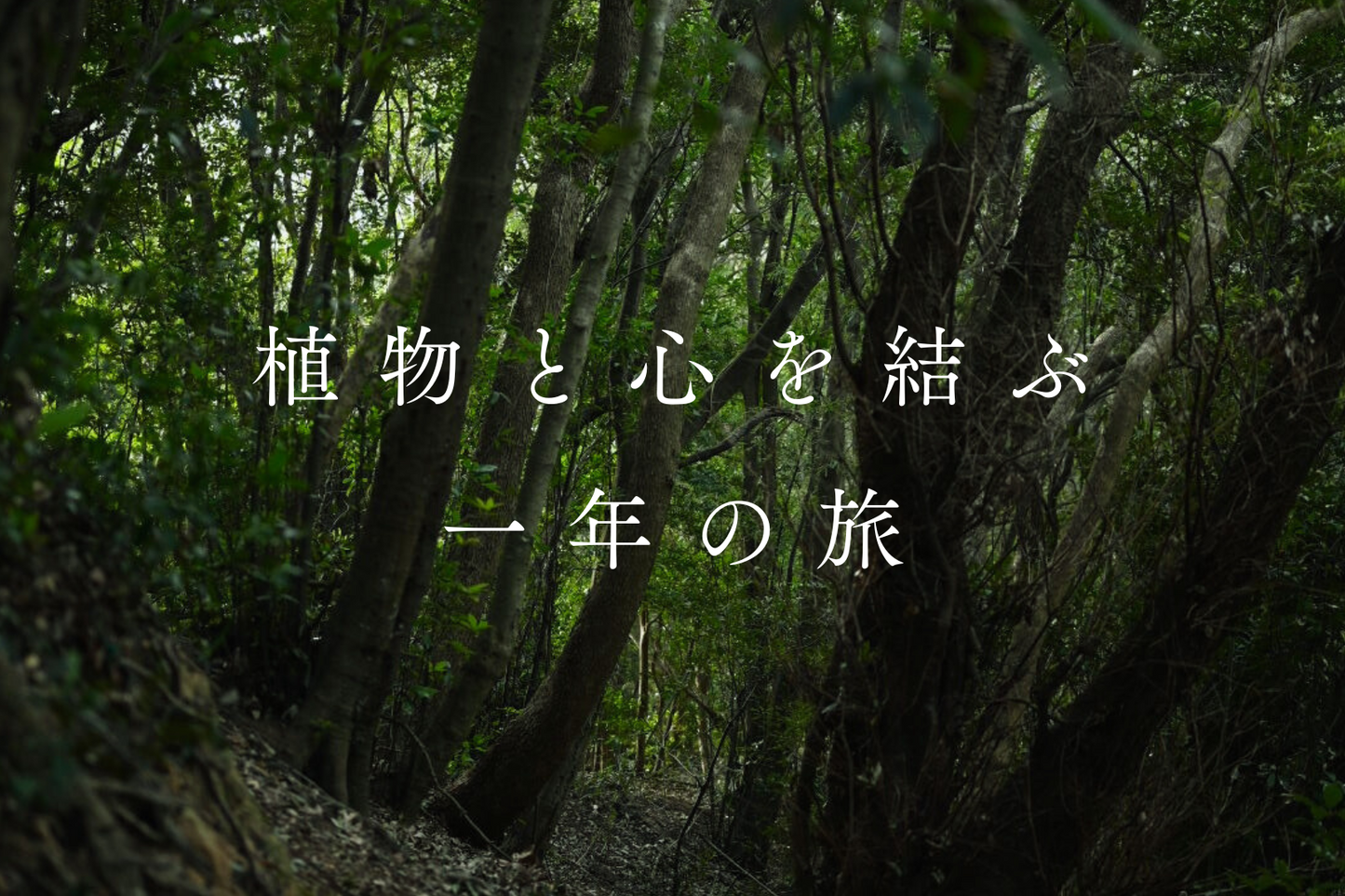薬草コラム
植物と心を結ぶ一年の旅
4/13満月。 本日、満を辞して 参加者自らが、共に学んでいく ‐ suu ‐の実践型コミュニティを開きます。 ✔︎ 春夏秋冬の野を歩き ✔︎ 植物たちの見分けを学び ✔︎ 季節の手仕事を楽しみ ✔︎ 美味しさや香りを味わいながらも... 〈植物と心で繋がるー〉 そんな1年間。 オフライン・オンラインを通じ 春夏秋冬、共に野を歩き 私がお伝えできるものをすべて 少人数のメンバーさんに向けて さまざまな形でお届けします。 ここから一緒に、 植物に逢いにいきましょう! 共に野を歩きましょうー。 山奥でなくても、 遠くへ行かなくてもいい。 "街中でいい"のです。 なぜならば、 まだ、気づいていないだけで 植物はありとあらゆる場所に 息づいているから。 お庭で、畦道で、 駅の周りで、街中の空き地で、 都会の公園で、線路沿いでー あなただけの“野”を みつけ、歩きましょう。 学び、知り、気づき 見つめ、触れて、味わい、感じて その先に辿り着くのは “すべての植物が愛おしく見える世界”ー。 一度あなたが 深く知った植物は、 もう単なる草ではありません。 道端で力強く生きる姿に 出逢えば たまらなく美しく愛おしく感じ その一瞬で驚くほど 心が温かく 満ちることでしょう。 いつもの日常なのに 目に映るものが変わり 何も変えていないはずなのに 日々が感動に溢れる。 まるで、映画が モノクロからフルカラーに変わったかのように。 やさしいけれど、壮大な始まり。 私の人生の景色が変わったように きっと、あなたの人生の景色も 色鮮やかに変わります。 そんな一生ものの旅路へ みなさんをお誘いしたいと思います。 〈このプログラムに来てほしい方〉 植物を愛するすべての方 植物を学んでみたい方(初心者〜OK!) 植物を学んでいたり、お仕事にしているが、もっと深めてみたい方 単なる野草の活用にとどまらない、その奥の世界を感じたい方 自ら学びを進められる方 - suu -の世界観が好きで、主催者とたくさん遊んでみたい!という方 一緒にコミュニティを創っていく、そんな気持ちのある方 なぜか強くピンと来た…という方 〈植物と心を結ぶ 春夏秋冬のガイドプログラム〉では オフライン・オンラインを通じ 春夏秋冬、共に野を歩き 私がお伝えできるものをすべて 20名のメンバーさんに向けて さまざまな形でお届けします。 満月の今日...
【ご報告】これまでのこと、これからのこと《後編》
(〈前編〉の続き) 春の風に背中を押されて 小さな決意が、動き出しました。 後半では、‐ suu ‐のこれからについて。 そしてその前に少し、 わたしのこれまでをお話しさせてください。 目次: I. 生立ち II. 糸島へ III. 植物に出逢う IV. 予想外のギフト V. その先に VI. 次なる願い I. 生立ち 私は1986年、東京生まれ。 多摩川や等々力渓谷にほど近い 緑豊かなエリアの出身です。 東京といえど、小さい頃から 自然好きの祖父に連れられて 野生の桑やビワの実を食べたり、 ふきのとうやツクシを採ったり、 椎の実をおやつにしたり... そんな幼少期を過ごしました。 (東京にも桑の実いっぱいあるんですよ) 祖父は庭いじりも好きだったので お庭はいつも、季節の果実や花々でいっぱい! 梅、フィジョア、柿、さくらんぼ、姫林檎 ブルーベリー、甘夏、無花果、柚子など... 庭の色とりどりの植物たちが いつも季節を教えてくれました。 (在りし日のお庭) 植物に囲まれていただけではなく たくさんの動物とも過ごした幼少期。 自然な流れで 獣医を志したのは、小学校低学年。 単に動物が好きだからだけではなく 生命体の仕組みだったり、 病気になる原理であったり、 治っていくプロセスであったり、 そういう自然の理(ことわり)に 興味が尽きなかったのです。 その気持ちは大人になっても変わらず わたしは夢を叶えて 動物のお医者さんになりましたが 新卒で入社した先は 超がつくほどの激務病院。 入社1年も経たないうちに、同期は全員辞め 私も数年で限界を迎えて 臨床医の道を離れることになります。 何年も猛勉強して 夢を叶えたはずなのに 沼の中を泳いでいるような苦しい日々...。 そんな毎日の中 助けを求めるように わたしは1度目の結婚をします。 そしてその流れで 大学院に進むべく渡米するのですが 気付けばなぜか ITの道に進むことになりました。 渡米後、1年ほど過ごした場所は 起業ブーム真っ只中だった サンフランシスコ。 街全体が熱気に包まれていたその時代、 世界中から集まる人々の 多様な生き方に触れた私は 私も、自分の心に従って生きてみたいー そう強く願うようになりました。 そうして、帰国と同時に東京を離れ、 ビビッときた糸島に移住します。 今から11年前の話です。 II....
【ご報告】これまでのこと、これからのこと《前半》
こんにちは。- suu - の佐々木美帆です。 春のはじまり、 SNSで 「そろそろお茶作りは卒業かもしれません」 と書いた私の言葉を、 たくさんの方が受けとめてくださいました。 心配してくださった方、 「どんな選択でも応援しています」 と言ってくださった方、 そして何より、「このお茶には代わりがない」と 涙が出るような声を寄せてくださった方ー。 ありがとうございました。 今日は、そんな皆さまへ、 あらためてご報告と、 気持ちをお伝えさせていただきます。 目次: I. - suu -のお茶作りの裏側 II. 揺れ動く III. これからのお茶作りについて I. - suu -のお茶作りの裏側 - suu -のお茶作りは 足元の野草に恋をした私が 庭のよもぎを摘むところから始まりました。 そこから8年ほど。 気づけば、 山の中に1500平米のよもぎ畑を構え 素敵なスタッフたちにも囲まれ 何万人もの方にお茶をお届けしていました。 糸島の隅っこで作りはじめたお茶が 口コミだけで広がり、 憧れの方々に飲んでいただいたり 国境すら超えて、 いくつものミシュラン星付きレストラン、 有名ブランドのアトリエやホテルでも 提供していただいていること...。 今でも夢物語のようで、 なんだか信じられません。 ですが 少しずつ規模が大きくなる中でも 変わらず大切にしてきたことがあります。 それは、 _すべて手しごとでのお茶づくり _作り手の五感を通じたお茶づくり そして _素材ひとつひとつと丁寧に向き合うこと。 - suu -では現在、 常時20種類ほどの お茶の素材を使用していますが、 特に、キーノートとなる素材については 農家さんや摘み手さんと信頼関係を築きながら 旬のタイミングで収穫したものを 吟味して使っています。 一年を通して鮮度が保てるよう、 厳密な品質管理のもと 毎回のお茶作りで微細な調整を重ねることで “いつも同じ美味しさ”という安心 をお届けしてきました。 ですが近年、気候変動や物価高騰に加え、 農業従事者の高齢化も進む中で、 これまで信頼関係を築いてきた 提携先の縮小や廃業が相次いでいます。 お茶づくりをする環境は、 年々本当に、厳しくなっています…。 私自身も、 さらに植物と深く繋がりたい もっと学びたい、という気持ちが芽生えていて もしかすると今は お茶作りを手放すタイミングなのかもしれない― そんなふうに考え、 辞める決意を固めていました。 II....
よもぎから桜の香りを引き出す ー - suu -の微発酵茶の話
待ちに待った、秋よもぎの収穫期がやってきました!
よもぎを丁寧に製茶すると
不思議と苦味や青臭さが消えて
花の香りー、
特に桜のような香りのお茶が生まれる、と気づいたのは、
- suu -を創業してすぐのこと。(※)
ですが自分のやっているたくさんの工程のうち
一体何がそれを生み出しているのかは
なかなか分からず
ここ1,2年で
やっとそれが〈微発酵〉によるものだと
紐解けるようになってきました。
ー
中でも特に
秋よもぎの新芽が生み出す香りは
芳醇で、深く、華やか。
お茶にしてゆく旅路の中で
苦味や青臭さがふっと消え
代わりにコクのある甘みが現れ
じんわり、沁みるように美味しいー。
そのため- suu -では、どのお茶にも
微発酵させた秋よもぎをブレンドしています。
よもぎ茶を作り始めて7年以上が経ちますが
・茶としてのよもぎを追求する、
・よもぎから花の香りを引き出す、
こんな変わったことをやっている人は
世界中探しても、ほかに出会うことはなく
当然、文献や知見もないので
数えきれないほどお茶を作り
時には緑茶での文献や、中国茶の論文、
よもぎの成分分析と化学式を基にして、
推測と実験を繰り返してきました。
身近で、よく知った植物のように感じるよもぎですが、
本当に、どこまでも、奥深いのです。
ー
香り成分だけではなく
クロロフィルも豊富な秋よもぎ。
その翡翠色の葉が
朝露に輝く姿は
息を呑む美しさー。
みなさまにも
伝わりますでしょうか….
ー
※ 桜の香りは、クマリン系物質によるもの。
実はごく稀に、ジャスミンの香り(おそらくジャスモン酸)を
引き出すこともできるのですが… これは本当に難しく...
まだまだ、道半ば!
#微発酵
#微発酵よもぎ茶
#よもぎ茶
#クマリン #ジャスモン酸